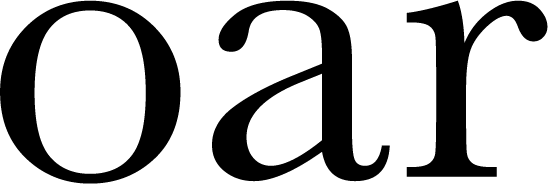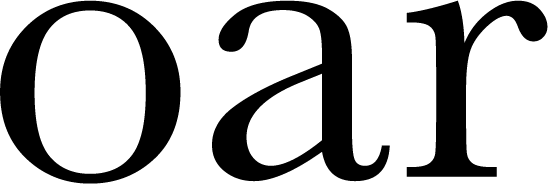第一回

写真とは何か。禅問答のような問いなだけで、正しい答えなんてない。けれど、応える者の志向が分かる質問となるだろう。多くの人は思い出や記録について触れるかもしれない。写真や美術を学んだ人たちは、表面、層、時間、空間などのメディア的側面を言葉にするかもしれない。記録メディアは、デジタル化を含めると多様な側面が浮上し複雑化している。僕は「写真とは何か。」身の上話をするように、メディアに対する今の考えやスタンスを話したい。話した先に会話となる筋道が見えるだろう。
僕なりに記録メディアに対して言葉にしてみると、「記録は、目の前の泉から湧き出る水を掬ったコップと水」のようなもの。コップはある一定の情報を含んだ器であり、その器には容量といった上限がある。同時に、とめどなく過ぎ去っていく物事や時間から切り離された断片的な存在となる。
ただでさえ多くの情報がこぼれていってしまうのに、二次、三次と情報が広がっていくと、どのようなものに変化していくのだろうか。話を聞くことや資料にあたることは、そこにはない、不在の対象と向き合うようなものだ。それは、失ってしまったものや過ぎ去る時間そのものを想像する試みではないだろうか。
僕は7歳の頃、阪神淡路大震災を体験した。大きな揺れで起きた両親に無理やり起こされたのを覚えている。余震を恐れて屋外の駐車場まで移動した。日が昇るまでの間、安全そうな場所にいたかったらしい。何が起きているのか落ち着かない状況の中、僕は海のほうから煌々と明るい様子を見た。その明かりは火事によるもので、夜明け前の景色を照らすように燃えていた。街そのものが松明となり、街中を照らしているようだった。
僕は文章にするまで、その明かりの中に人がいることに気がついていなかった。あるいは、見ないようにしていたかもしれない。被災して以来、明け方の青と赤に彩られた空模様は、景色が燃えているようで違和感を抱き続けている。
28年以上が経ち、かつての惨状が残っている地域は少なくなった。当時を知る人が減っていく一方で、知らない人たちが増えている。大学の非常勤講師をしていた際、学生と話していて彼らが阪神淡路の震災を体験していない世代であることに小さな溝のようなものを感じてしまった。以来、自分が被災者であり、語り部であることを意識するようになった。かつて起きたことをどのように残し、伝えられるか。記録メディアには「ここにないものがあることを伝え、想像させる力」がある。
しばしば見知らぬ人から「写真、撮ってください」と声をかけられる。一人で過ごしていても、知人と過ごしていても彼らはお構いなしにやって来る。申し訳なさそうな顔をして近寄ってくる動きは、鹿を射抜く矢のように一直線だった。瞬間的に出会い、去っていく。僕は一連のやりとりを整理するため、その場に立ち尽くしてしまうのだった。
手短な会話からスマートフォンが手渡され撮影を行う。彼らとやりとりを終えたあと、手元から離れた写真はどこに行くか想像してみる。家族や知人、恋人と共有したり、SNSに投稿してオンラインを漂うことになるのか。外付けのハードディスクやクラウドに保管するなどして個人の管理の下におくのか。はたまた気に入らなくて消してしまうこともあるかもしれない。いくつもの可能性を想像することはできるが、結末を見ることは叶うことはないだろう。
手元にない写真については思い出せないが、彼らと出会った場所のことは憶えている。フィールドワークや出張先、知人の案内などで立ち寄った景勝地で彼らと出会ってきたのだった。場所や景色が僕と被写体を繋ぎ、その時その場でしか築けないイメージを作り上げ、残滓のように残り続ける景色が僕の中に染み入ってくる。
2年ほど前の春、撮影の仕事で長野県に長く滞在していた時のこと。当時、僕は撮影の合間を縫って蛇にまつわる土地を巡っていた。湖や川など、水に関わる場所が多かった。その話を仕事先でしていると、山でも蛇と関連する場所があると長野市の戸隠神社を勧めてもらった。そこは蛇ではなく、龍を祀っているという。
神社の整備された参道の脇を見ると、岩や石が多く土砂崩れの名残らしきものを見た。大小の石がごろごろと横たわっている様子から土砂崩れと連想したのは、かつて天竜川で見た石と似たものを感じたからだ。
長野県諏訪市にある諏訪湖を水源とした天竜川は、暴れ天竜と呼ばれるほど頻繁に土石流や洪水が起きてきた。植林やダム建設などで治水を行ったとしてもたびたび氾濫し、今でも暴れ竜の一端を覗かせているという。実際に、天竜川を訪ねた際、細かな砂に大小さまざまな石が転がっていた。もし洪水が起きた場合、水と石がうねり動く様が蛇や竜のように見えるかもしれない。それ以上に飲み込まれる感覚を想像しただけでも恐ろしく思えた。
川に来る前、飯田市美術館で「三六災害(*1)から60年」といった企画展を見た影響かもしれない。伊那谷を襲った大水害の歴史資料、近年の洪水の映像から飯田市で起きた水害について学ぶことができた。過去や事例を知らなければ、ただの砂と大小の石が転がっている茫漠とした川辺に見えるだろう。
2019年に山口県に滞在していた際、台風の大雨の影響で千曲川が氾濫していた。食堂のテレビで水害のニュースを見ていたのを覚えている。際限なく水が広がっていく映像を見て、知人の実家のことを心配しながらも、流水に押し流される墓と遺骨について考えてしまっていた。かつて墓や遺骨があった場所で故人を偲ぶことはできるのだろうか。場所と記憶の結びつきが散らばることで、死者に対する想像や感情の結びつきが難しくなってしまうのではないか。
松谷みよ子の『民話の世界』では、「例を上げれば数かぎりなく、私たちの周囲に洪水に苦しめられ、水と闘ってきた物語はころがっている。それに気づくかどうか、大切に思うかどうかは、私たちの中に、その視点があるかどうかであろう。」と綴られている。民話だけでなく記録と記憶に向き合うことに対する切実な思いが込められた一節だろう。(*2)
戸隠神社の奥社からの帰り道、鏡池を案内する地図を見つけた。少しだけ遠回りすることになるが、寄り道することにした。池に着くと水辺のせいか、吹き抜けた空間に出たからか、肌を裂くような寒さだった。周囲に人影もなく、山から吹き下ろす風が水面に触れて小さな波が次々と生まれていた。鏡池と呼ばれるほどの水面の反射を見ることはできなかったが、青い若葉の木々と雪を被った山々の景色が美しかった。冷えを覚悟してしばらく景色を眺めていると、背後から声をかけられた。
あのう、写真を撮ってもらえますか。
振り返ると中年男性が立っていた。黒い革のジャケットとパンツ姿でツーリスト風の装いをしていた。慣れた一連のやりとりから手渡されたスマートフォンを覗くと、撮影モードの画面には、黒い革と淡い色の背景で首から下がシルエットとなった男が写っていた。風景に穴が空いているようだった。
写真を何枚か撮り、スマートフォンを持ち主のもとに返す。男はお礼の挨拶を済ませそそくさと去っていった。彼は撮った写真をどこに連れて行くのだろう。僕は写真の行方が気になり始めた。その夜にSNSのハッシュタグを用いて#鏡池と検索をかける。グリッド状に写真が一覧となって大量に表示されるが、壮大な鏡池の風景ばかりが投稿されていた。鮮やかすぎる彩度、鏡池らしい鏡面状態の水面。小さな画像でも目につきやすいイメージのようで、自分の目もその色などに引き寄せられたことに驚く。何度かスクロールしてみたものの、池、池、池、ときどき人間。といった具合だったが撮影した男性はどこにもいなかった。会った人にだけ見せているかもしれない。首から下がシルエットとなっている自身の姿にギョッとして見せないでいるかもしれない。投稿されなくても様々な理由が想像できてしまう。いつか思い出を語るための写真になるかもしれない。記憶の中の鏡池は今も穴が空いたままで、写真は今も行方知れずのまま。
(*1) 三六災害
昭和36年(1961年)6月、長野県南部の伊那谷、天竜川流域で起きた大災害。
梅雨前線の停滞と台風の接近による影響で大雨が降り、飯田観測所では1週間で1年の3割を越える雨量を観測した。伊那谷各地で氾濫や土石流、地すべり、山津波が起きた。土石流によって家や田畑が押し流されるだけでなく、消えてしまった集落もある。
(*2) 『民話の世界』松谷みよ子 講談社学術文庫 P.40
長野県でフィールドワークを始めてから、民話に触れる機会が増えた。なかでも水に関わる民話が多く語られている。なかでも水害が背景にある『黒姫物語』にはいくつものバージョンがあり、その一つに松谷みよ子が採話した物語が取り上げられていた。彼女が同県で民話採訪をしてまとめたものが本著である。著者の民話への関心からはじまり、語りを考察することで見えてくる歴史背景、現代の民話の在り方まで幅広く書かれている。
守屋友樹 | もりやゆうき
写真家。2010年日本大学芸術学部写真学科卒業。写真の古典技法や古写真に関する歴史を学び、実地調査で過去と現在を重ね見る体験をする。かつてあった景色や物、出来事、時間などを想像する手立てとして不在や喪失をテーマに制作を行っている。 https://yk-mry.com/