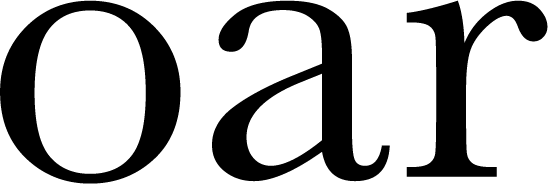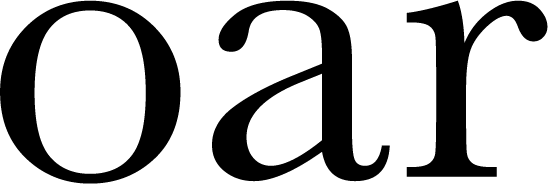第二回

7歳の記憶を振り返ると、震災で亡くなった友人の声が思い出せなくなっていることに気がついた。その時、僕の中にいた友人がより遠くに行ってしまった気がした。どのような顔で、どのような声をしていたのか、逆光で顔が見えなくなった時のようにいつまで経っても様子が分からない。死んだ鹿が野鳥たちに啄まれるように、皮から肉、内臓と中に収まっていたものがやがて消え、骨だけが残る。やがて骨さえも風化して、何もなかったかのように消えていく。
ホテルのルームナンバーを忘れるのと違って、誰かに教えてもらうことすらできない。いったい何をきっかけに思い出すことが出来るのだろう。他者に伝えようのない声の輪郭や、一緒にいた時間の日差しといった触れられない「触れ」が僕の内部でこだまし続けている。忘却によって喪失したものの周辺を丁寧に想像していくことで、失ったものそのものに迫ることは可能なのだろうか。同時に、ところどころ欠落した記憶を維持するためには、虫食いの記憶を足場にステップを踏むように何度も繰り返し思い出すしかない。穴が広がっていくか、何かを思い出し塞がっていくのか、忘却に抗うには都度思い出すことが重要とされる。しかし、記憶に対して疑いを持ち始めてしまうこともあるだろう。「思い出す記憶は確かなものなのだろうか、単なる思い込みだったり、妄想かもしれない」と。取り戻せない記憶を繰り返し思い出すことは、確証できない内なるものから確かさを得ようとする行為である。それは孤独で深く、それでいて穏やな祈りとなる。
友人は小学一年生の時の同級生で、幼馴染と仲がよかった。一人遊びが好きであまり友人と関わらなかった僕をいれて三人で遊ぶことが時々あった。どこで何をして遊んでいたのかは覚えていない。今も記憶に残っていることが一つあって、それは友人と勉強した時のことだった。
昼過ぎに行くと約束した友人の家を訪ねると、幼馴染も相手の親もいなかった。なぜだか居心地が悪くなったのは、幼馴染を仲間外れにしたような気持ちになっていたからだろう。案内された部屋は6畳ほどの和室で、ちゃぶ台と背の高い洋服箪笥が一つあった。全体的に茶色く子供の部屋と思えない簡素さだった。僕らは背の高い箪笥に見守られるような位置に座り、黙々と漢字の練習をした。時々、何かを教えてもらっていたがその話の内容や顔の様子は霞がかったように不鮮明な一方で、窓から差し込む日差しが暖かく、僕の鉛筆を持つ左手に生えた産毛が白く輝いていたことを鮮明に覚えている。そのあとの記憶は途切れてしまい、どのように過ごし帰ったのかが欠落している。
僕の人生で初めて撮った写真は、「阪神淡路大震災の自宅の様子だった」ということにしている。
20代半ばを迎えた際、制作テーマを見直したくなり、実家にあるアルバムを全て見ることにした。写真を主なメディアとして扱うには、自分が初めて撮った写真の原体験について知りたいと思ったからだ。2010年を迎えて以降、およそ10年ほどの間はエミュレーションなどを用いたデジタル写真の表現が盛り上がっていた時期だった。僕も写真の古典技法を学んでいたことから、イメージと物質、身体の関係から作品を作っていただけに、その流れに近さを感じていた。
デジタル写真は、様々な物質や状態へと出力可変であると同時に、エミュレーションによってデジタル画像そのものの物性にも触れている。例えば、画像加工で100枚の写真を合成したとする。すると、画像の生成や崩壊が見えてくるだろう。デジタル画像は、エミュレーション、出力方法、支持体をどのように組み合わせても結果的に写真の物性が表面に現れ出る。
一方で写真における古典技法のダゲレオタイプや湿板写真は、反射が強く、あるいは透明度が高いため図像が見えにくい。一般的な写真のプリントに比べてよく磨かれた銅板やガラス板に定着した写真というものは、図像よりも支持体が前に出てきてしまい、見えにくさを解消するために鑑賞者が見やすい位置を探すことになる。つまり、写真はそもそも見えにくいもので、見るためには体を使うこと、素材と図像を行ったり来たりする錯乱的な眼差しが根底にあった。
イメージと物質の関係、厳密に言えばこれら二つは全く別物だ。しかし、僕が古典技法を学びながら実際に用いるのではなく、現在の技術を用いて見えにくさを扱っていたから近さを感じていたのだろう。
それが写真表現の枠だけの話だと気がついて、当時の僕は写真というジャンルに捉われないテーマが必要だと感じていた。これまでのメディアに対する形式的な制作手法から一度離れ、フィールドワークやリサーチから見えてくるアイデアやコンセプトを主とし、個人的関心と断片的なナラティブを緩やかに接続する、普遍的なテーマに関心を持つようになった時期だった。
アルバムは、戦時を思わせる大叔父や大叔母の様子から始まり、若かりし両親の姿や幼少期の自分の写真など、パーソナルな記録に溢れていた。その中で目に留まったのが荒れた部屋の写真だった。画面全体にあらゆるものが散乱し混沌としている。物の散らばりから、震災後に撮られたことが分かった。地震そのものが写らないことに気が付くと同時に、亡くなった友人のことを思い出していた。イメージと関連しないことを思い出すのはどうしてだろうか。写真を見ることは、目の前の図像だけを見ていることにはならない。それだけ複雑な動きをしながら記憶を引き出しているのかもしれない。
リビングでうたた寝をしていた母に、見つけた写真について質問すると「覚えていないかもしれないけど、撮ったのはあんたよ」と言われた。
写真は目の前のものを記録するという性質であると同時に、記録されなかった物事もある。記録されなかったものを想像することはとても難しい。見えないものを想像するために、様々な記録を辿るうちに誰かの記憶に触れることになるだろう。それによって喚起されるイメージは何か。それは、おそらく記憶と記録の間にある手触りのようなものかもしれない。決して言葉にしきれない記憶のニュアンス。
ラッパーで時事問題などのコメンテーターとして活躍するダースレイダーの著書『イル・コミュニケーション』(*1)で、2018年に亡くなったECD(*2)の葬儀に参列した際、『ラッパーの葬式』(*3)という曲を思いついたきっかけが述べられている。「ーーECDのレコードを、CDを、カセットテープを、データを、記憶を再生すればいつだってECDはお前の前でラップをして見せる。ーー」音源を再生し続けることで、たとえ死んだとしても聞き手の中でECDは生き続け、さらに世代を越えて記憶を繋いでいくことが可能だと指摘している。もちろん音楽などの記録メディアに限らず、法事などのセレモニーや思い出の品、モニュメントに立ち会うなど、その時々のタイミングで故人を偲ぶことが再生に繋がるはずだ。
1月17日、朝から撮影の仕事で忙しない一日だった。この日は阪神淡路大震災から29年が経つ日で、今年も神戸市で追悼式が行われたニュース番組をYoutubeで見ていた。高齢化が進み、20年を区切りに追悼式が途絶えていくなか、震災を知らない世代も交えて活動を続けている「阪神・淡路大震災1.17のつどい」を取り上げていた。いつか追悼式に参加したい気持ちがあるのと裏腹に、日々の忙しさにかまけて一度も行ったことがない。育った土地の一つであるにも関わらず、自分のルーツをおざなりにしているようだ。それでも、モニュメントも何もない部屋で、日付という数字から震災が起きた日と失った友人のことを思い出してみる。
傷ついたCDを再生した時のように、曲が飛び飛びに流れるようでなんとも頼りないものだ。震災からおよそ30年という時間の経過がもたらしたのは、友人の死に対するショックが和らいだことと、被災に対して「あれから」と距離を置くような態度が現れたことだろう。
スマートフォンに表示されている時間を見ると9:00手前を示していた。そろそろ出発しないと予定の時間に間に合わない。僕は気怠い身体に勢いをつけて起き上がり、身支度を済まして家を出る。
(*1) 『イル・コミュニケーション―余命5年のラッパーが病気を哲学する―』 ダースレイダー ライフサイエンス出版 (引用箇所 p.180)
脳梗塞と代謝性アシドーシスで入院し、腎不全と糖尿病を抱えて見えてくる世界をポジティブに提示してくれる一冊。不謹慎かもしれないが笑ってしまう話がいくつもあったのは、病を抱えたとしても生きる楽しさに満ちている証だと思った。
(*2) ECD
ラッパー。97年に行われたHIPHOPイベント、さんピンCAMPの主催者(提唱者)として知られる。
また音楽活動に並行して執筆、政治運動などの活動を行っていた。2018年に逝去。
(*3) 『ラッパーの葬式』
歌詞の中で再生という言葉を英語でplayと訳さず、Resurrection(復活)だと言っていたのが印象的で、音楽に限らず記憶が宿るものと個人の関係について考えるきっかけとなった。ビート漫談『うなぎ』もおすすめ。
守屋友樹 | もりやゆうき
写真家。2010年日本大学芸術学部写真学科卒業。写真の古典技法や古写真に関する歴史を学び、実地調査で過去と現在を重ね見る体験をする。かつてあった景色や物、出来事、時間などを想像する手立てとして不在や喪失をテーマに制作を行っている。 https://yk-mry.com/