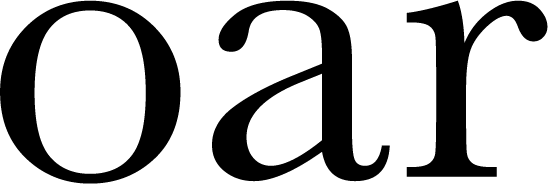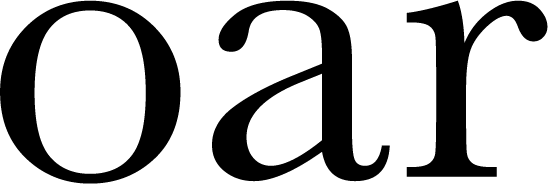地獄から届くセルフィー。併存するオポジットミラーズ

2022年2月、NASA(アメリカ航空宇宙局)はひとつの画像データを宇宙から受信したことを発表した。それはジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope、以下JWST)が、自らの望遠鏡の主鏡を写したセルフィー(自撮り)だった。
ー
ーー
ーーー
私は宇宙の地獄で
遠いその地で目覚めたわたしは、今まで体験したことのない辺りの暗さに体を強張らせた。目を開いたかどうかも分からなくなるその状況で腕を伸ばしたが、手には何も触れられず、空気にさえ接する感覚もない。まるで真空で宙吊りになっているかのようだった。そして同時に、その伸ばした腕の片側だけが明るく照らされている事に気が付く。銀色の腕はすぐさまハレーションを起こして、反射した光は暗闇に吸収されていった。腕は早々に熱を帯び始めて、腕を引っ込めたくなったが、そうすると今は腕で遮られていた光がちょうど顔に当たることになるから動かすのを取りやめた。そのまま影に覆われた顔は凍りつく冷たさで酷く痛んだ。そんなことをしていると、ふと自分がその場所にたった独りだと気がついた。独りっきりーーの地獄。孤独に耐えられず、おもむろにカメラを取り出した。わたしはカメラを持っている。
ー
2021年12月25日12時20分、ギアナ宇宙センターから1基のロケットが打ち上げられた。その日、JWSTは宇宙で最初に誕生した星(ファーストスター)を探すミッションを果たすべく長い旅に出発した。NASAが過去に打ち上げたグレートオブザバトリーと称される4基の天体宇宙望遠鏡(ハッブル宇宙望遠鏡もその中のひとつ)の後継機でもあるJWSTは、度重なる計画延長の末完成した。ハッブルの100倍ともされる性能を誇り、18枚の特殊な反射板からなる六角形の巨大な主鏡は、130億光年の距離から放たれた赤外線が観測可能だ。JWSTは地球から月の距離よりもはるか遠くの160万キロの位置で太陽や地球の外側を周回し、観測の邪魔になる主に太陽からの光線を防ぐ為の遮光板を背負っている。テニスコート一面分のその大きな菱形遮光板に隠れる形の望遠鏡部は暗闇に包まれてしまう。明けることのない夜を旅する孤独の始まりだった。
ー
カメラのファインダーを覗くと、遠くの暗闇の先に砂粒がひとつだけ浮かんでいることに気が付いた。赤青黄に、針で刺したようなほんの小さな光が点滅している。それを皮切りに無数の砂粒がポツポツ現れ始め、一様に点滅を繰り返しながら砂粒は連鎖するように増え始めた。砂は点から線へ、線から帯になり、帯は別の帯へ繋がっていった。そしてついに画面全体を埋め尽くして、たったひとつの砂粒が光の砂漠になってしまった。大量の光の波は眼球の湾曲に沿ってへばりついて、視界を真っ白にしていく。暗闇から明転した状況に、さっきまでの孤独感は嘘のように無くなり、今度は光を放つその砂漠の砂一粒一粒への興味が私の頭を埋めつくしていった。あの砂はどこから来たのか、そんなに光ってどうしたんだ。そんな果てもなくどうしようもない問いの解答は、この孤独の砂漠で誰にも邪魔されないだろう。ゆっくり身体を預けた真空のベットは音も空気も風も遮り、横たわってファインダーを覗き続けるための最高の治具になる。カメラを構えてわたしはひたすらシャッターを切り続けた。私は光を捉えることに夢中になった。
思いつきで、カメラのレンズをこちらに向けて、シャッターを切った。撮れたかどうか確認すると、そこには暗闇の中に私の顔だけがうっすら浮かび上がっていた。撮れてはいたがピントが合っていないようだ。少しブレている気もするし、なぜか一部だけやけに光ってしまっている。ピントを合わせる方法も分からなければ、ズームアウトも出来ないーー。何度も試したが同じ写真が取れるだけだった。この場所と私の姿を写したい。私は今ここにいると伝えたい。その一心だった。ここは地獄なんかじゃない。
ーーー
ーー
ー
僕は地上の地獄で
冬の里山、葉の摩擦音が息を潜めて静まり返った林。あるのは土壌の十分な湿気と、十二分な微生物、植生。それらは光を餌に光合成を繰り返しやがて自ら餌となる。見上げて目を細めれば、葉のない木々の幹が大雑把に縁取られてしまうほどくっきりとした存在感だ。顔を腐葉土の地面に近づければ、茶色い葉緑体の呼吸が鼻先にこそばゆく触れる。鷲掴んで放り投げれば数ヶ月ぶりの酸素を得た土壌が窒息手前の深呼吸で唸りをあげる。
空(から)などあり得ない密度でわたしの手の届く範囲でさえ複雑に密集し、全く静かに思えたこの場所も、積層されて圧縮された沈黙に私は安らぎよりも孤独感を感じた。おそらくこの森のずっと遠くまで行っても同じだろう。この場所において僕は圧倒的に余所者で、自然はひたすら僕に無関心だった。たった一人でここにいる。孤独だ。
「ここは地獄か」
ネガティブの上澄みが捻じ切られて声に出る。場違いな発声は立ち並ぶ木々の隙間を縫って一目散に逃げ出してしまう。音の行方を片耳で追いかけると、灰みたいにみるみる窄んでいるのが聞こえる。早々に迷子になって最後、それは静かに腐葉土に落ちてしまった。

堰を切ったように孤独は葉の軋む音で弾け飛ぶ。腐葉土の光合成のフローが組織や過程から分裂されて逆再生され始める。草と土、土と風、風と酸素、酸素と葉緑体、葉緑体と光、光と太陽。地上は8分前の太陽の残像を頼りに活発化する。それは常習的に遅延された製造過程が成す景色だ。見上げて目を細めれば、さっきの枝だけの木々が葉を生い茂らして擦り合わせ始める。腐葉土に近づけた顔は過去から来た光の反射に照らされて熱を帯びる。葉緑体の細胞組織は数時間後に暗転する夜空をガイドする星座表の姿で現れた。真空の宇宙の風がここから吹き出しているとは…鼻先にこそばゆく触れる。腐葉土の深呼吸の唸りは、もはや地球に届いたゴールデンレコード※の再生音に思えたーー。
孤独地獄はとっくに遠くに放り投げられていた。余所者なのは皆同じ、辺りの過密さのミクロに砂粒みたいなそれぞれの個性が見え始める。ここで僕はたった独りで、他(者)もまた独りだ。僕はずっと前からここにいた気がする。それだけ心地の良い孤独感だった。ここは地獄なんかじゃない。
ー
ーー
ーーー
宇宙から届いたセルフィー
NASAは以前、JWSTに自撮りは不可能だと説明していたーーカメラ機器を担当するチームの責任者は、星の光だけでこのような画像を撮れるか確証が取れなかったことから、撮影成功は驚きだったと語った。地上と同調するように送られてきたそのセルフィーは主鏡を正面からまじまじと捉え、真暗闇を背景に写る表情は一向に構わない様子で、JWSTの孤独を写していなかった。真空で何もなさげな空間に位置したその余所者は、不可能に思われていたセルフィーを用いて自分がそこにいることを強く私たちに伝えようとしている。
「ここは孤独で地獄。しかし過密で無関心な孤独の賑やかさは、ここの景色を見る為には欠かせない条件だ。私のカメラは僅かな光も捉えられるから全然大丈夫。そう。ここは地獄なんかじゃ…」
そう訴える姿は、私たちとJWSTの間にある果てしない距離など簡単に縮めてしまうほど生々しい。宇宙が驚くほど近くにあるように迫り来る様相だ。そして繰り返し地獄がそこにあると言う。そして、無いとも言う。
ー
ーー
ーーー
フランシス・ポンジュは『動物相と植物相』の詩の中で、まるで植物の隣人であるかのように彼らの地獄について綴っている。
彼らは…でない。彼らは…でない。
彼らの地獄は違った種類のものだ。
…
彼らは声を持たない。彼らは身体不随であるというのに近い。ーー「彼らは自分の姿勢(ポーズ)によってしか自らを表現しない。」
…
無意でありつつ彼らは、彼ら自身の形を複雑ならしめることに、彼ら自身の身体を、分析の最大複雑性の方向に完成することに、自らの時を過ごす。
地獄はその者しか知らない。そしてその地獄の生き方は、JWSTや私たちにとっての地獄とまるで合わせ鏡だ。植物が不動性によって居場所を決定づけられ、その条件から出来得る最大限のポーズと手段をとることで、彼らはいっこうに仕合わせだとポンジュは意図する。
人には人の、赤ん坊には赤ん坊の、ダニにはダニの、渡り鳥、キツネ、アリにはアリの世界。それぞれの生得的知覚範囲と実地的経験の作用する世界の総体の中「環世界」に生きているとユクスキュル(1864年–1944年)は考えた。私たち人間には知覚できない世界がすぐ目の前にあり、私たちの世界はむしろ世界の片隅にあるのだろう。私たちの地獄もまたそうだろう。
遠方から届くセルフィーは、宇宙のはるか遠くの探査機と、冬の里山と、根を張り動かない植物とーー私たちの環世界をトレースさせる。同じ場所にいることで見える景色を、異なる環世界とイコールに繋ぐ。植物と、はたまたJWSTと並行して異なるだけのこのインスタントなこの単独行為は地獄の救世主となるだろう。地獄でセルフィー。自分の居場所を記録する。光はそれぞれのカメラのレンズに入射し、そのセルフィーが写すのはその場所で生活をすることとと変わりないものだ。わたし達は今はただここにいる、ことしかできないのだから。横を見れば、合わせ鏡の奥の誰かと目が合うだろう。
ーーー
ーー
ー
ー空白の味方
空白を埋める方法は、宇宙の地獄に何も「ない」を「ある」で埋めることであり、「遠く」を「近く」に見ることでもあり、「大きい」を「小さい」に見つけることだ。また、それらは逆もしかり。私たちのいる地上では、音は振動する限り無くなることもない。想像の許す限りの小さな耳を手に入れて音を積み重ねて目の前に残置させて後から聴こう。森の中の蟻にとっての遠くは、僕らのたった一歩で到達するし、宇宙の遠くは光の速さで何億年もかかる足元で転がっている。一粒の砂粒で巨大な砂漠に降り立つ夢を見る。そして合わせ鏡の奥の暗がりに別の地獄を見つけ出す。
ポンジュの書いた「物の味方」は、「物」の目線でポンジュ自らそれらと語り合い、その世界を念入りに書き留めてきたかのような叙情的ルポルタージュだ。「空白の味方」では、「物」さえ無い空白や余白、間(ま)、の”なさげ”に存在する”ありげ”を書き留めた。何もなくてもそこでシャッターを押す。たとえ地獄みたいな孤独の暗闇であっても、そこを埋め尽くす空白の密度を感じ取れるはずだ。空(から)の地獄はどこにもない。空白に味方することは、空に見える空白を前に、並走して遅延して重なって離れて消えてしまうあれとこれのどっちつかずの関係を繋げることにただ一生懸命になることだ。そこに何かがあると僕はただじっと期待し続ける。
2023年3月
参考:『生物から見た世界』ユクスキュル,クリサート著 , 日高敏隆,羽田節子訳 岩波文庫 2005年
引用:DG Lab Haus「次世代宇宙望遠鏡、初の天体撮影 「セルフィー(自撮り写真)」も」2022年2月12日掲載https://media.dglab.com/2022/02/12-afp-01-4/(2023年2月6日閲覧)
引用:『フランシス・ポンジュ詩集』阿部良雄編訳 小沢書店 1996年より
※ 1977年に打ち上げられた2機のボイジャー探査機に搭載された金メッキされた銅レコード。地球外知的生命体に向けて人類の文明の様々な情報を記録している。秒速約17.027kmで飛行中であり、地球から最も遠くにある人工物体。
大石 一貴 | おおいし かずき
1993年山口県生まれ。彫刻家。Studio&Space「WALLA」を共同運営(https://walla.jp)。2018年武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻コース修了。国際水切り大会8位。https://www.kazukioishi.com