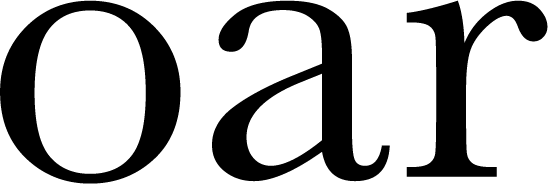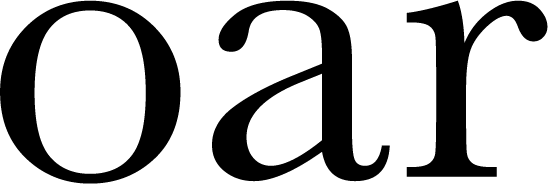ある道端の吸血“木”と、圧縮して同厚のドップラースケープ

ある道端のその場所は、つんざく轟音から音量を絞り切ったみたいな空間だ。とでも言えば良いのだろうか。けたたましい静けさが空間を占拠していて、こちらが耳を傾けても何ら応答せず、気に留めない様子で、
「どのあたりでしょうか?少し風が吹けば確かに静かに数万の葉の摩擦音が聞こえてきそうで、野球ヘルメットを被った子供はもうすぐ土手を登り切って振り返り、仲間に何かの合図を送り始めることでしょう。遠くの低い山々には一体幾つの杉の木があるのでしょうか、冬の騒がしさがここまで伝わってくるようですが、わかりません。ただ、ここは程よく辺りが開けた土地のようで、想像でしか掛け合わせることが出来ない音声が当たり前のように同居しています。」
想像で……とは何のことだったか。それは風が強く吹いて裏返ったとある葉だけが起こす風切り音であり、離れたの大都市のビルのガラスに映る誰かの口元の動きであり、異国の地で鳴る時報の鐘を初めて耳にする事であり、そして遠い多方面から届いた音源が、音速に等速で鳴り止まず、時間の先頭にあるという事だったりだ。
ずっと止むことのない音があるとすれば大発見だ。一度だけ振動したらすぐに聞こえなくなる事を当たり前に知っていて、私たちは取りこぼさない様に躍起になってしまう。観測器の感度を常に無限に高くし続ければ、オシロスコープの画面はいつまでも波打つのだろうか。誰かが発した音を今でも聞き続けている事を実感できるのだと、少し声に出して想像してみる。
ー
ーーこの’’積層’’は振り出しに戻れないので、しつこく堆積する事になる。
ーーー
この場の鬼門と見える杉の木が2本、互いの首を少しばかりもたれ掛けている。この傾きは、上に伸びるとともに高くなる装飾的な頭の重さが原因だろうか。そもそも頭部の重さは動物の、特に人間の特性というのが当たり前だった。この2本はいつからか、重たげに葉を生やしたその首のあたりで交わってしまった。季節が変わって葉が減っても離れられず、そのおかしな捻り方によって人間のごとく首を痛めるかと思いきや、片方の活動の源を余すところなく欲する吸血“木“に身紛う様子でその首根っこに食らいついき、養分を吸い取る音を延々と出している。
止むことのない音は隠し通さなければならない。
実施。
ひとつ、騒がしく、ふたつ、騒がしく、みっつ、騒がしく。
並立する白い2つの看板の文字が、読み易そうなフォントを使って、看板の筆者が発した言葉の声質を終わりなく曳きずり始めた。2つの看板の距離感からは筆者はそれぞれ別人であることがうかがい知れる。同じ方向を向いた、別人の声の投擲は、文言に相応しいフォームで今もまだその手から離れず切り取られた動作の途中みたいにメリハリとした説得力でファールボールを注意喚起している。
重ねて、離れた大都市のビルのガラス窓に映る誰かの姿が太陽の反射で一直線になった。読唇が可能になり、晴れた空にうってつけの”影送り”で、あの人の言葉を読み辛そうなフォントで書き写してしまえる。目を閉じれば暫くの間、見知らぬ言葉が体内で発光し始めることになる。夜が来れば、言葉は一度空に回収されて、次の晴れの日までここで待ちぼうけるに違いない。書き順など関係なく、文字の輪郭から浮かび上がることでしょう。
重ねて、傑作の土遊びが始まる。乾燥した小道には、何度も道脇の草が侵入しようとしたが引き返している。広い土地を求めるのは、見晴らしが良かったり、心地が良かったりするからではない。暗がりの地下では目隠しした状態で迷路を進む。壁伝いに歩くしか方法がない状況では、まさか壁から離れて歩き始める決断をすることはないだろう。その先には常に踏み固められる荒野が広がる。行きたくても行けない、僕らが足踏みする壁際の土は耕され肥沃で、とっておきの遊び場になってしまった。賑やかな足踏みの音が聞こえる。
積層の断面に隠匿は困難だ。
吸血”木”は吸血鬼らしからぬゆったりとした動きのまま音を出し続けた。木は身近でありながら、生き物としての幅広な時間感覚と代謝の連続性を見せてくれ、まるで永遠の姿だと思わせる。
ー「自分だけがここに取り残されたみたいだ」

あれから7ヶ月が経った。
小道には相変わらず草が生えておらず、しかし脇へ行くにしたがって鬱蒼と生え広がっている。
土遊びは盛り上がった。”影送り”の文字は未だ浮かび続けている。
7ヶ月の時間の懸命な努力は、吸血“木”に何ら影響しなかった。夏の葉を茂らせ、今もなおその太い首へ寄りかかってしまっている。
ーーー
ーー
ー
あれから7ヶ月が経っていた。
ここで必ずあの音が聞ける筈だ。
辺りの様子は変わってしまっても、この木の影に老化の姿は重ならない。
時間は遠くへ進むと言うし、加齢を成長過程として考えれば問題ないと言い聞かせれば。
フランシス・ポンジュは『霧の境域の中で樹木たちは解体する』の詩の中でこんな一節を記している。
「きわめて若い時からして、自分の生き生きした特性や、身体の部分を放棄することは、樹木たちにとって、日常の営みとなっているのだ。」
やはり吸血“木”などいないのだろうか。
ポンジュの執念深い樹木の代謝の観察は、日常の営みというルーティーンを通して、時間の方向を無しにしていない。摂取だけでは停滞するだけで、棄てていかなければならないことを当たり前だとしている。
ー声に出してしまっても本当に棄てたことにならない
摂取と放棄が繰り返し起こる。時間の方向へ溢れた出来事は限られた土地や空間なのだから、ならば放棄は小さく小さく積んで残置してその場に納め続けるしかない。音声も同時に増え続ける。ただ当たり前に振動はすぐに止んで手持ちの計器で拾えなくなるのだから、想像の許す限り小さな耳を手に入れて、許されない接種の放棄の休息によって圧縮された出来事と音声などを同厚に留め置くことが、聞こえた筈の音を聞き続ける為のとても良い方法だったりする。吸血“木”はまだここにはいないみたいだ。
2022年8月
引用:『フランシス・ポンジュ詩集』阿部良雄編訳 小沢書店 1996年より
大石 一貴 | おおいし かずき
1993年山口県生まれ。彫刻家。Studio&Space「WALLA」を共同運営(https://walla.jp)。2018年武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻コース修了。2022年8月からルーマニア、ブカレストにAIRで滞在中。国際水切り大会8位。Official Site:https://www.kazukioishi.com