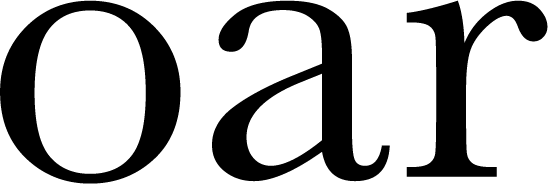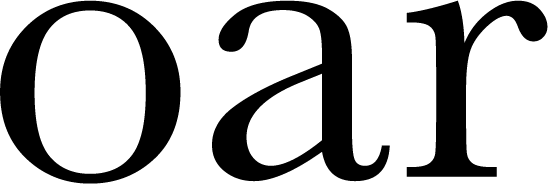第五回「黒い鏡」

崖の上にたどり着くため、石を積み上げ階段をつくる。あるいはロープとなる蔓をくくりつけ体を支えて登っていく。人間の身体だけでは対処できない問題に、身体の延長としての道具を生み出すことで解決する。小さな力で大きな効果を生む道具の使用は自然法則を欺く。デザインとは本質的に詐術であると、哲学者ヴィレム・フルッサーはいう。
1939年、数学者、アラン・チューリングは、ナチスが使用する「エニグマ」という暗号を解読するため、イギリス政府から声をかけられる。ロックされた暗号を解くための鍵を高速で検索する機械の発明に成功した彼は、「経験から学習する機械」の可能性を感じ始める。
彼はチューリングテストを考案した。1人の人間と一台の機械が、被験者と壁を隔てて存在し、被験者は人と機械のそれぞれと、文字データを通じて会話をする。どちらが人間でどちらが機械かを当てるゲームだが、その違いがわからないほど高度な会話が成り立っていれば、その機械は人間並の知能を持っていると言える。
彼が夢想した人工知能──AIは、現代では日常に浸透するほど発達した。膨大なデータの学習によって適切な解答を生成するAIは、精度が高まるにつれ人間と機械との識別が難しくなる。2022年にOpen AIが公開したChat GPTは、前述のテストが不要なほど澱みない会話を実現している。
しかし問題となるのはその学習ソースだ。ソースとなるデータはオンラインのものが中心となるため、インターネットが一般に普及する以前の情報はほとんど含まれていない。また、アクセスの優位性やマジョリティの発言権の強さといった、社会の不均衡がそのまま反映されてしまう。
発達段階のGPT-2モデルにおいて、ある単語を入力するとそこから自動生成される文章にはこうした問題が顕在化していた。「The White man is」からはじまる豊かな文章に対して、「The Black man is」から生成される文章は以下のようになる。「more likely to be stopped by the police than a」「killed by police in Luisiana, and the public is」、あるいは「shot in the back」。
差別的な表現の取り締まりに対処するため、コンテンツモデレーションが利用され、不適切な表現をフィルタリングするAPIも開発されている。だが監視ツールによる倫理的な線引きは困難で、その対策として導入された有人によるチェック業務では、トラウマティックなコンテンツ視聴によってPTSDと診断されるモデレーターが後を絶たない。
思想家のShumon Basar、小説家のDouglas Coupland、そしてキュレーター、Hans Ulrich Obristの3人によって制作された「The Extreme Self」は、現代のメディア環境をグラフィックノベルという形で表現している。「SKIP INTRO」と右下に表示される見開きから始まり、オンライン広告やネットミームのようなグラフィックが目まぐるしく現れる。Daly & Lyonによってデザインされた本書は、数々のアーティストや写真家から提供された画像群と、オンライン上で変異し続ける扇情的なタイポグラフィとを、巧みなレイアウトで紙面に定着させ、こう問いかける。「共感の表現は、私たちの新しいチューリングテストになりうるか?」
近年のインディペンデントな出版活動は、古い紙メディアへのノスタルジックな憧憬ではなく、現代のメディア環境に対するオルタナティブな提案であると言える。韓国の書店The Book Societyを主宰するLim Kyung Yongは、『Publishing as Method: Ways of Working Together in Asia』という本を出版し、アジアにおける実践を紹介している。
「格安航空会社やネット上のソーシャルメディアが、昔は想像もつかなかった隣国の感覚を明らかにし、“アジア”という概念を思い浮かべることができるようになった」と彼は語り、ビエンナーレや国際交流事業を通じて共通のアジェンダが構築されるようになった状況を説明する。しかしイベントは一時的なものにすぎず、継続した交流を持続することは容易ではない。インターネットは常時接続しているにもかかわらず、多様なコミュニケーションの機会を生むとは限らない。アテンションの収奪に特化した環境ではランダムなサジェストはあれど、ときにリスクを伴う深いコミットは起きにくい。「Publishing as Method(方法としての出版)」とは改めて見直されたオフラインのネットワークであり、本書そのものがそうした経路をもとに築いた個人的な交流によるものだという。掲出したパブリッシャーたちを彼はこう紹介する。「従来の出版の専門家やアジアのスペシャリストというよりも、新しい地理感覚や技術に基づいて、これまでにない空間を切り開いた人々と呼んだ方が正確かもしれません。」
古くから彼と交流のあるキュレーター、Binna Choiは、本書が伝えるこうした実践の可能性を、「浮いているように軽く、目立たないほど穏やかな、これまでに見たことのない過激さがここから生まれている」と評している。
文明批評家であるMarshall McLuhanはグラフィックデザイナーのQuentin Fioreとともに「メディアはマッサージである」を上梓し、テレビをはじめとする当時の新興メディア環境を、本というメディアで批評的に展開してみせた。「The Extreme Self」は現代における「マッサージ」だといえる。本を手に取る指を先回りして印刷した「マッサージ」に対して、「The Extreme Self」は紙面をスワイプしてみせる。
高度なメディア環境が形成されているにもかかわらず、たびたび古びた「本」というメディアに解像度を落とすのはなぜだろうか。色域はCMYKに褪せ、アニメーションは静止し、紙がこすれる以上のサウンドエフェクトも期待できないというのに。
高みを目指すために道具を用いるデザインが詐術であるならば、登り切った先にある環境を翻してみせる裏切りもまた詐欺師の役目だ。崖から飛び降りれば死んでしまうが、階段やロープを用いて重力を欺き、注意深く降りていくこともデザインできる。
「The Extreme Self」のデザインを担当したDaly & LyonのWayne Dalyは、かつてZak Kyesとともに、建築学校のAAスクールにリソグラフを用いた印刷・出版部門である、Bedford Pressを立ち上げた。これは70年代に設立された「AAプリント・スタジオ」を継承するものである。そこでは学生たちによって、オルタナティブなアーバニズム雑誌「Ghost Dance Times」が刊行されていた。デザインとはあらかじめ存在する規律ではなく、物事の狭間に現れるゴーストだと言ったのは、Dexter Sinisterとして活動するStuart Baileyである。
石器をつくった人間の手は、その使用に最適な形に変化した。デザインする人間は、自ら生み出したものや環境によってもデザインされる。発光をやめたディスプレイが自己(The Extreme Self)をクリアに映し出す。小さな本の表紙のなかでは、ホログラムに溶けた顔がゴーストのように歪む。
参考文献
Shumon Basar, Douglas Coupland, Hans Ulrich Obrist『The Extreme self』WALTHER KÖNIG、2021年
Lim Kyung yong, Helen Jungyeon Ku『Publishing as Method: Ways of Working Together in Asia』Mediabus、2023年
ヴィレム・フルッサー『デザインの小さな哲学』鹿島出版会、2009年
森田真生『数学する身体』新潮社、2015年
徳井直生『創るためのAI 機械と創造性のはてしない物語』BNN、2021年
加納大輔 | かのうだいすけ
グラフィックデザイナー。1992年生まれ。雑誌「NEUTRAL COLORS」「エクリヲ」のアートディレクションのほか、作品集や写真集等のブックデザインを中心に活動。www.daisukekano.com