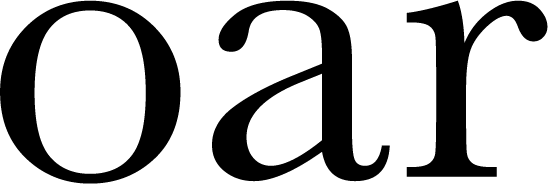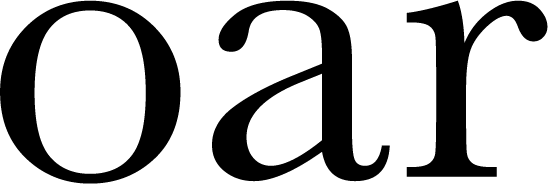第二回「ブラインドタッチ」

地球の姿を初めて見たのがいつだったのか、今ではもう思い出せない。もし1968年を生きていたなら容易に特定できただろう。編集者、スチュアート・ブランドによって創刊された雑誌『ホール・アース・カタログ(WEC)』に、それは初めて掲載されたからだ。軍事機密であった写真の公開をブランドはNASAに要求した。地球の姿が人々の目に触れたのは雑誌の表紙を通じてのことだった。暗闇に浮かぶ青い球体が、いま私たちが立っている惑星だという実感をどれだけの人が持ち得たのだろう。
『WEC』は“Access to Tools”をテーマに掲げていた。ツールへのアクセスを民主的に行うためには情報の透明化が必須であり、私たちの住む惑星の可視化はその手始めの作業だった。のちのインターネットを先取りした『WEC』は、ペーパーバック版のグーグルだとスティーブ・ジョブズが称賛したほどだ。
地球を目にしたとき、複雑な模様を描く球体よりもそれを取り囲む黒々とした宇宙に恐怖を感じたことを覚えている。宇宙に空いた穴のようにその惑星の姿は映った。
1976年、マサチューセッツ工科大学(MIT)の教室の壁に穴が開けられた。「Messages and Means」と名付けられたクラスの学生たちが、オフセット印刷機と写真のプリプレスルームを隔てる壁に業を煮やし、自由に行き来できるよう破壊してしまったのだ。このクラスの教鞭を執っていたのはミュリエル・クーパー。学生たちに直接機械や道具を操作させ、体験と思考のフィードバックループを起こすことが有効だと彼女は考えていた。活字や製版等の細かな作業に自身でアクセスすることが学生たちを自由にした。工程上の制約を取り払い、プロセスのなかからアイデアを発見し、専門性の境界も溶けていった。印刷機を占拠した彼らはその場限りのプリントを次々と生み出した。
「一度印刷にコミットすると、大きなコストなしに戻ることはできない。ミスは取り返しがつかない。オプションは最小限。クリエイティビティは、プロセスの最初の部分に限定される。(略)これは、オフセット印刷に限らず、コンセプトと製品の間に機械があるすべての活動において言えることだ。」
大量生産においてプロセスの途上に特殊なアイデアを反映することの難しさにクーパーは言及する。彼女は機械と人との関係を再構築することを目指し、やがてその試みは「Messages and Means」から「Visible Language Workshop(VLW=可視言語ワークショップ)」というクラスへと発展する。
はじめ印刷や写真術に特化していたVLWは、技術的な進展に伴いCGを扱うようになる。機械と人とのインタラクションの追求に機材を限定する必要はない。相互関係を粘り強く見つけ出そうとする彼らにとって、コンピュータはより高度なフィードバックを可能にするものだった。印刷機もコンピュータも、ユーザーのために可視化されたインターフェースを生み出すツールだと捉えたクーパーは、印刷機をハックしたように今度は電子空間を飛び回った。3Dグラフィックスを操る彼女のコックピットの助手席に座っていた学生は、VLWについて「数百万円のおもちゃがある遊び場のようだった」と振り返る。
可視化は理解を助ける。二進法の数字の羅列をアイコンに置き換えることで、人は現実世界とのアナロジーによって電子空間を旅する。平等なアクセスへの志向はWECからも引き継がれる倫理であり、特権階級の独占に抗する民主的な理想であった。水面を覗くように情報を見通す。こちらの情報とあちらの情報を等しく交換する。
大企業とプラットフォーマーに支配されたオンライン空間のどこかに、まだこうした倫理は見つけられるだろうか。検索窓に入力した情報はすべてトレースされ、そのデータがどのように利用されるかを記したアルゴリズムは不可視である。情報のフィードバックは画面を挟んで対称形を描くはずが、スクリーンの先に映る自分は自分以上の大きさに膨れ上がる。
「世界は画像において表象する、と限定する。では画像とは一体何なのか、スクリーンである。スクリーンに向かう光ではなく、スクリーンに衝突して描かれた何かしらの空間が画像である。」
雑誌『スフィンクス』の創刊にあたり、グラフィックデザイナー・戸田ツトムは宣言した。印刷、製版上のプロセスにノイズを侵入させた誌面デザインを数多く手がけた彼は、やがてCGに関心を持つようになり、霧がかった湖や森の風景を画面の先に現出させる。現実世界の模倣を目指したのではなく、模倣の過程で起きる齟齬に彼は関心を向けていた。正確に数値化しなければ思い通りの像を描けないからこそ、曖昧に捉えていた感覚と向き合わざるをえない。なぜ、これはこのように見えるのか。微細な感性の検証を機械との接触によって迫られ、画面の先の重力を持たない虚像が現実の像に潜む厖大な情報量を意識させる。電子風景との対峙を彼は、「重力のほとり」と表現した。
スクリーンに映る自分はこちらを模倣しているようで、すでに別人に成り代わっている。入力情報の変換過程を知るため水面を覗き込んでも、視界は暗く濁ったままだ。フィードバックは非対称に変化した。均衡は崩れ水位が上がる。水の中で重力は不確かになり、感触は泡に消える。
「9.11の、あの事件のあの映像への対応がまだ終わっていない、そこから先に進めないでいる気がします。」
刺激に感性を支配され応答を迫られるなかで、わからないまま保留し、予感を投入する時間を持つこと。戸田は事件から5年の時を経てそう答えている。
「グラフィックデザインの機能のひとつには「明示する」ということがあります。ただそれはローカルな状況であってけっしてテーゼではない。明示を受けた「視る者」は、想像してはいけない、という指示も同様に受けたことになります。」
テレビのスイッチを入れて何かが像を結ぶ。それまでの瞬間こそ最も情報量が高いことを彼は指摘する。2001年9月11日の同時多発テロを報じた影響力のあるメディアはまだテレビであった。世界中の誰もがひとつの映像を同時に視聴するという体験は、やがて訪れるオンライン上の惨事の共有へと繋がってゆく。
2003年、「テロとの戦い」を大義に掲げ、大量破壊兵器を保有しているイラクから国際平和を取り戻すという口実でアメリカはイラク戦争を開始した。受け止め方にためらう間もなく、一連の映像は多くの人々を悪に対する復讐心へと駆り立てた。
写真家、Geert van Kesterenは2003年から2004年にかけてイラク戦争を記録した「WHY MISTER, WHY?」という本を出版する。勇ましいアメリカの報復劇を伝えるメディアとは裏腹に、ほとんど関係のない市民が殺害されている惨状を写真は伝えている。何度も再生される刺激的な映像は私たちが求めたものだろうか。最適に処理されたプレゼンテーションの受信を強いる力学から距離を置き、視ることの主体性を確保することは可能だろうか。
Mevis & Van Deursenによってデザインされたこの本の小口は鉄格子のように、あるいは絶望しきった市民の心のように傷つけられている。ページを繰るため傷口に触れる。次のイメージを見ようとするたび薄いコート紙は張り付いた傷を引き剥がされペリペリと音を立てる。見開きに配された写真はテキストページの挿入によって分断され、英語とアラビア語のテキストはそれぞれ左から右へ、右から左へと走り出す。二つの言語が交錯する見開きを閉じればまたひとつの物体に戻り、裏へ返すとタイトル文字は重なり合って配置されている。矛盾を包摂した、重力を伴ったイメージ。本の形で現れる写真が語りかける情報は視覚的な刺激以上の背景を意識させる。
情報との接触の微細さ、フィードバックの深度を取り戻す方法はどこにあるのだろう。「WHY MISTER, WHY?」。ふたつの疑問詞に挟まれたまま答えを見つけられず、再び本棚へしまう。
参考文献
David Reinfurt and Robert Wiesenberger『Muriel Cooper』The MIT Press、2017年
『ユリイカ 2021年1月臨時増刊号 総特集◎戸田ツトム ―1951-2020』青土社、2020年
Geert van Kesteren『WHY MISTER, WHY?』Artimo、2004年
加納大輔 | かのうだいすけ
グラフィックデザイナー。1992年生まれ。雑誌「NEUTRAL COLORS」「エクリヲ」のアートディレクションのほか、作品集や写真集等のブックデザインを中心に活動。www.daisukekano.com