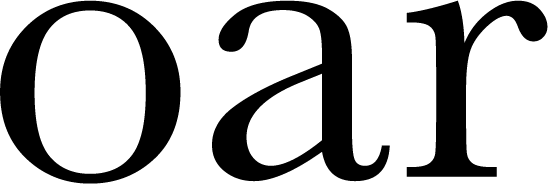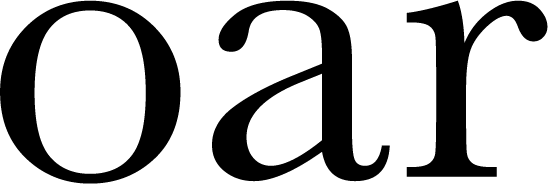第六回

今年は震えるほど寒い日がなかった気がする。制作などで寒冷地に行くことが多い僕にとって深刻な変化だった。気象庁の発表によると、寒い日が減り、暑い日が増えていく傾向だという。いつか冬を失ってしまうことを想像すると、網走の流氷 (*1)や諏訪湖の御神渡り (*2)などが見れなくなるのも時間の問題だろう。やがてその光景も文献に残された言葉とイメージだけとなった未来が訪れるかもしれない。そうなる前に見れるうちに見て、記憶に留めたいと思うようになった。
御神渡りは、零下10度ほどの冷え込みが数日続くと凍った湖面が轟音を伴ってせり上がる現象とされている。諏訪大社上社の神が下社へ通った痕跡とも言われ、八剱神社の宮司と氏子らが氷の亀裂を観察し、その年の吉凶、天候などを占い記録している。移動する神の姿は龍蛇とされ、せり上がった氷のうねりが蛇の姿を連想させる。現象が物語を見出したのか、あるいは物語が現象に意味を見出したのか、神事の成り立ちを考えるとメビウスの輪のように回帰してしまう。
諏訪湖は地殻変動によって陥没して出来た湖であり、糸魚川静岡構造線と中央構造線といった断層が交差している他、いくつかの断層に囲まれている。急峻な山々に囲まれた盆地であるため、かつては岡谷市の麓から茅野市にかけて水に満ちていた。湖には31本の流入河川があり、そこから流れ込む砂によって縮小、開田や治水などを経て現在の姿に至る。流入河川の数の多さに対し、水が流れる先は天竜川の一つであるため、治水が難しく古くから現在まで水害が度々起きてしまうのだった。
蛇は古代から生と死を象徴する生物とされてきた。瞼の無い輝き続ける眼、繰り返される脱皮、毒を持つ牙、四肢のない身体をくねらせて移動する姿、どれも人々にとって異質で恐ろしい特徴に思えただろう。諏訪および八ヶ岳山系から出土する土器には、蛇の模様が刻まれたものが多数あり、一説によるとこれらはマムシがモチーフと言われている。マムシは他の蛇と違い、腹の中で卵を孵化させて総排泄腔から5、6匹を出産する。人間の出産過程と比較し、その生態から見えてくる強烈な生命力にあやかりたいという願いが込められているのかもしれない。
凍結した湖が割れる音を初めて聞いて以来、僕は湖が割れる音を蛇の歩く音として録音するようになった。何度も諏訪湖に通ううちに自然環境、文化などの歴史が蛇の表象と関わっていることが見えてきた。それは普段から目に見えているものではなく、御神渡りといった現象として現れ、厚い氷が割れる音によって多層的な歴史が再生される。諏訪湖は大きな記録装置であり、再生装置でもある。このまま温暖化が進み、冬のない未来を迎えた際に過去をどのように再生することが出来るのだろうか。これまで蛇の足音を録音していると思っていたが、蛇の形をした記憶を拾うようなものだと意識が変わり始めている。これから拾う蛇たちは、いつかの再生を待つ場所としてオルゴールのシリンダーに収めて眠らせるのだろう。
凍った湖面に誰かが何かを投げたようだ。柔らかい管が震える音が辺り一面に広がった。諏訪湖はなぜだか柔らかな音がする。膨張と収縮を繰り返していると、しなやかな氷になって音を柔軟に響かせるのだろう。凍結した湖は大きな楽器のようで、何かを投げ込めば誰もが奏者になれる。僕も先の人に倣い、足元に転がっていた氷の欠片を投げてみた。色彩や時間が吸い込まれた灰色の風景が緩慢に震えた。
氷が落ちた先を眺めていると、幾つもの氷の塊が転がっているのが見えた。落ちることも溶けることもできず、氷が惑星となってその環を延々と作り続けているようだ。宙吊られた惑星たちは人々に投げられた時間の断片であり、その瞬間の記憶が込められている。似た記憶が集合していながらも、決して繋がることなくいずれ溶けて消える。日々の生活から生まれる記憶たちが邂逅することは稀なもので、出会えたことがささやかな奇跡と言ってもいい。たとえば、2025年1月24日の諏訪湖は春を思わせるように温かく、波には無数の太陽がゆらゆら揺れているような一日だった。そんな様子を記憶した人とどこかでまた出会うことはできるのだろうか。その時、その場所にいた人の数だけ記憶と言葉があることを想像する。僕はある人から聞いた話をメモに残そうと記憶を振り返ると、よるべない話の海でひとり泳いでいた。
ーーY市の寺で「寿」に模った蛇の抜け殻について語る住職。
昔、私が庭を掃除していた時に綺麗に脱皮した蛇の抜け殻を見つけました。その時は、なんとなくパズルを収める額に入れ床に寝かせていました。それからというもの、私の身体に異変が起きたんです。吐くわ、下すわ、原因不明の体調不良となってしまいました。心当たりがないかぼんやりと考えていると、頭に蛇が降ってきました。驚いた私は、蛇に関わる何かがないか考えました。それで床に寝かせたままだった額を思い出したんです。頭よりも高いところに掛けると、悪かった体調はすっかり良くなりました。以来、私は庭先で蛇の抜け殻を見つけるたびに「寿」と象って額に収めるようにしています。
ーーAさんから聞いた話。
私が嫁いだ先での話。結婚して旦那の実家に住み始めた頃、蛇が出るようになりました。姑に言われるがまま蛇を捕まえて、家から離れた場所まで連れて行き、蛇を放しました。しかし、何度やっても家に戻ってくるわけです。家の場所を覚えているようで非常に聡い生き物だと思いました。家族とは「もしかしたら、この家の主なのでは?」という話となりました。それからは、主(ぬし)さまとして受け入れ共に住むことを選んだのです。
「あ、一番星だ。」夜の薄皮が張り始めた頃、僕は北側の空で眩く光る一点を見つけて大きな声を出してしまった。普段いる場所よりも一際明るくて大きな粒に見えたからか、驚きと喜びが声となって溢れたのだろう。隣で凍った湖を見ていた友人のMは、「どこどこ」と言いながら首を上へ傾けた。僕が指を差してみたけれど、Mと共有できていたのか分からない。確かさがないのは一番星も同じで、北極星のように予め決められた星ではなく、その日にその人が初めて見たものが一番星と言われている。もしかしたら、僕と違う一番星を見ていたかもしれない。
「暗くなったし、そろそろ帰ろう」Mに声をかけると、友人の顔は濃紺の暗闇に沈み、表情が読めなかった。もう一度声をかける。
「コーヒーでも飲んで、それから星を見よう」
ーーニジヘビ
友人のぬかずきが住む町を訪ねると、前日の大雨でその地域一帯が土砂崩れに飲まれてしまっていた。幸い近隣に民家はなく、山に沿うように作られた道路だけが被害を受けたのだった。町は深い盆地状の土地で、その中心に大きな湖があった。その昔、大きな地割れによって地盤が陥没し、コップのように水が溜まって湖となった。満水の時は僕がいる場所よりも高いところまで満たしていたが、少しずつ減って現在の姿となったらしい。湖の底を覆う空は、偏西風の影響で雲が延々と東に流れ、天候は常に変化し続けていた。
ぬかずきとは、大学時代の同級生で別学科に所属していたが、選択科目の授業で隣になったことをきっかけに飲むようになった。酒の席で話す内容は、いつもお互いの研究内容が中心だった。アカデミックな話は、個人的な話を避けるための都合のいい道具だったのだろう。ぬかずきは自分のことを話さなかったが、僕の心霊体験を聞くのが好きだったようだ。
僕に霊感があれば何が見えたのか伝えられるのだけど、幸いそんな能力を持ち合わせておらず、落ちのない話をすることが多かった。彼に言わせれば、「落ちがないということは、まだ終わってない話なのかもな」と薄笑いしながらよく言っていた。
彼は怪談のほか神話にも関心があったのか僕に質問してきた。
「古事記の国作りの話みたいなものだけどさ、神が環境を作ったのか、環境が神を作ったのか考えてしまうことがあるんだけど。うとくんはどう思う」
「民話ではさ、水害が多い地域だと竜や大蛇の怒りだと書かれていたりするけど、きっと当時の人が見た人の畏怖が現象に投影されたものだと思っている。けど、起源については僕の考えが及ばない話かな」
「心霊体験してるのに、やけにあっさりしてるな」
「ホラー映画でもさ、原因を追求すると状況が悪化するってことがあるでしょ。ああはならないように、自分の怖い体験は謎のままにして人に広めているだけ。怖さを共有して中和させるのが大事だと思ってる」
「要するに恐怖を伝搬させるってこと?」
「うーん、受け取り方次第でそう言えるかな。僕は互いに怖いねって確かめ合えるくらいがちょうどいいな」
彼は納得したのか、沈黙したまま小さく頷いた。
大学を卒業すると互いの住む地域が変わって会うことがなくなり、僕は知人のつてで美術作家のもとでアルバイトをするようになった。作家がギャラリーに在廊する日だけ同行し、作家に成り代わって来客に対応するといった内容だった。なんでも作家のプライベートを探ろうとする者への対策として身代わりを雇うことにしたという。
在廊する際は必ず羽織るようにと墨色のシャツとパンツが七着も支給された。灰がかった黒に薄ら茶が帯びたコットン地は目に優しく、鑑賞者に安心感を与えるために選択したのだろう。僕は着る服に困ることが無くなったことと、月の半分が休みになったので、持て余した時間を使うために旅行に出るようになった。
ぬかずきは地元の大学院に進学し研究を継続しているらしかった。定期的にぬかずきから電話がかかってきては、新しい怖い話がないか確認されるのが常だった。慣れない環境から来るストレスなのか、単なる暇つぶしなのか分からない。けれども、昨日の夜は普段と違って怖い話を求めての連絡ではなかった。
「うとくん、明日は休みだろ。面白いものが見れるから僕の地元まで来いよ」
彼は駅名だけ言い残して一方的に通話を切った。僕は後先考えず、早朝の特急を乗り継いでぬかずきを訪ね、災後の風景に遭遇してしまった。
山の地面に水分が多く含まれ、重力によって崩れたようだ。大小の岩がいくつも混ざっているのが見えて、断層が交差する土地なだけに複雑な地盤なのだろう。もしこの辺りに住民がいて、地すべりが起きたら甚大な被害になると予想できた。自分も巻き込まれたらと想像していると身体が緊張し硬くなっていた。部外者である自分が何も出来ずにいることの困惑と居心地の悪さで胸が苦しくなる。ぬかずきが何を見せたいのか意図が読めず、僕は彼に電話をかけてみる。コール音は鳴るがやがて留守番電話サービスに切り替わる。何度も試してみたが繋がることはなかった。
道路に目をやると、センターラインや境界線などの規制表示が見えないほどの土砂がアスファルトを覆っている。その道路を境に車や畑を耕す人などが行き交うのが見えた。見えない線が引かれたように、向こう側で起きたことに誰も気にも留めず、慣れた身振りで日常を送っていた。
土が乾き始めたのか砂埃が舞って風景が霞む。砂で舌がざらつく前に一区画離れ、もう一度ぬかずきに連絡しようとスマートフォンを出すと、土に覆われた縁石に腰掛けた老人に話しかけられた。
「にいちゃん、はやく帰んなさい。ここは危ないよ」
「すみません。僕はこの辺りに住むぬかずきの友人で、彼に呼ばれて来たところでした。昨日の大雨でこんな大ごとに」老人にかける言葉を探すうちに口篭ってしまった。
「あぁ、ぬかずきさんとこの知り合いだったのか。彼が今どこにいるのか分からないな。居場所も分からないし、にいちゃんはもう帰ろうな。たとえ探したとしても夜までには帰りなさい」
急かすように、町から離れることを勧めるのはなぜだろう。翁面のような笑顔は部外者がいることを快く思わないのか、本当に長居することを勧めていないのか、どちらの意図で話をしているのか分からない。老人は一度顔を合わせてから話をしていくうちに徐々に視線が下へと向かっていった。具合が悪くなったのか心配になり声をかけようとすると、老人は無言で人差し指をゆっくりと空に向けた。
彼の指の先には大きな光の環が浮かんでいた。無数の色を発し、留まることなく循環し続けていた。ハロ (*3)にしては重さがあるというか、どこか生きているように見えて違和感があった。
「たしか雨が降る前兆だったような。このあと降るかもしれないですね」
「あぁ、降るだろうね。絶対に」
「ハロをよく見るんですか」
「見る?違う、違う。見られているんだ。それに、この町ではニジヘビと呼んでいる。あいつはな。この町をずっと見ているんだ。毎晩、深夜になると大雨を降らせるのさ。おかげでこの辺りはずっと土まみれのままだ。いずれみんな飲み込まれる」
吐き捨てるように言った老人の声からは怒りと畏れが込められていた。
もう一度空を見てみると、無数の蛇の鱗が密集していた。秩序だったうねりが色と輝きを生み、中央に向かって宙を這い続けていた。隙間が見えない動きは一つの大きな輪を成し、鱗の輝きと思っていたものは蛇の眼だった。波のような照り返しが無数の色を作りだし、その色はとても美しくいつまでも見ていられた。同時に鏡に写る自分と目を合わせた時のような気味の悪さがあった。
煙草の煙に気がついて、老人に目を向け直す。匂いに気がつかなかったら、いつまでも見ていたのかもしれない。老人は視線を地面に向けたまま小さく呟いた。
「もう見るな。下を見て帰れ」
僕がゆっくりと地面に目を向けると、再び老人が口を震わせながら静かに呟いた。
「蛇はなぁ、人と違って瞬きしねぇんだよ」
スマートフォンの液晶に映る空を覗くと、蠢き輝く光の環が僕らを見続けていた。
(*1) 流氷
サハリン北東部の海が寒風によって凍っては流され、薄い氷は南に流されながら成長して厚みを得ていく、日本近海ではオホーツク海の南部にあたる北海道の稚内、網走、知床などで見られる自然現象。北海道に接岸する時期は一月から三月までの期間とされているが、その厚みは年々減っていっている。
(*2) 御神渡り
長野県にある諏訪湖において冬になると発生する現象の呼び名。氷点下10度を越える日が連日続くと、湖が全面凍り、日中と夜の寒暖差によって氷の収縮と膨張が起きることで轟音を伴いながら分厚い氷が割れてせり上がる。古くから神が通った跡とされ、諏訪大社の上社にいる男神・建御名方神が下社にいる女神・八坂刀売神を訪ねた痕跡と言われている。2018年以降、御神渡りは現れていない。
(*3) ハロ
暈(かさ)とも言い、太陽や月に薄い雲がかかった際、その周囲に光の輪が現れる光学現象。
雲の氷晶がプリズムとして働くため、太陽などの光が氷晶を通過した際に屈折して色が見える。
守屋友樹 | もりやゆうき
写真家。2010年日本大学芸術学部写真学科卒業。写真の古典技法や古写真に関する歴史を学び、実地調査で過去と現在を重ね見る体験をする。かつてあった景色や物、出来事、時間などを想像する手立てとして不在や喪失をテーマに制作を行っている。 https://yk-mry.com/