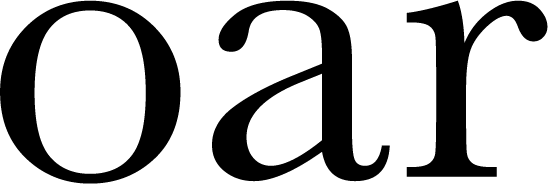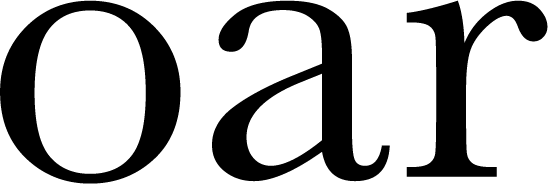第五回

信越地方の山間は、春でも肌が切れてしまいそうな冷たい風が吹いていた。遠くに見える北アルプスの嶺にはまだ雪が積もっているのが見える。深夜、レンタカーで山越えするのは難しいかもしれないと次の目的地について境内で考えていると、囃子の演奏が始まった。辺り一帯がゆっくりと緊張感に満ちていく。神輿を先頭に氏子たちが列をなして歩き始める。後を追うように皆ぞろぞろ歩き、十間ほどの大きな建物に着いた。氏子など関係者たちが中に入り、それ以外の人々は建物を囲むように立つ。礼服を着た地元の関係者たちもいれば部外者もいる。僕はなるべく邪魔にならない場所を選び見学することにした。
関係者と思しき人々を見ていると、視線が建物に集中しているのが分かった。僕も彼らに倣って視線を建物に戻すが、簾が下がっているのもあって中の様子が見えにくい。再び囃子が演奏を始めると、御饌が次々と運ばれていくのが薄らと見えた。祝詞と共に野菜や雉、鹿の首などが運ばれていく。一通り神事を終えると、供物だけを残して神輿を担いで本殿へ戻ってしまった。残されたものをゆっくり見物しようと建物に近づくと、中へ僕を招くかのように簾は春風で吹き上がり続ける。僕は盆の上に乗った鹿の首に自然と目を向けてしまっていた。中空を見据える目は、陽を映し生気が満ちたように輝きを放っていたのだった。
この祭りは、鎌倉時代もしくは江戸時代から続いていると言われている。当時は猪鹿75頭の首、雉、神酒などを神饌にしていた。現代の倫理や価値観に合わせ、動物の首は剥製に変更され数も三つほどに簡略化されている。神事の際に獣肉を捧げることが珍しいと言われるなか、とりわけ首を供物にしていることは思いもよらなかった。胴体を含めて供物にしてしまうと原始的な祭事になりかねない。頭部のみとなったのは、人々に荘厳さや畏怖を与えるための形式と効率が洗練された結果だと考えられる。鹿は、蛇、狐、狗などと同様に神使の動物だとされているが、その首を供物にすることは神聖性を剥ぎ取り、見えていなかった側面を露わにしているようだ。
鹿は、野うさぎなどの野生動物と同様に季節に応じて夏毛と冬毛が生え変わる。毛の太さや色が変わるだけではなく、春夏になると明るい茶色の毛並みに白い斑点模様が生える。その斑点は鹿の子と呼ばれ、木々の間から落ちる日の光に似せたものらしい。写真の原点とされるピンホール現象の一説で、アリストテレスは葉の隙間から差し込む円形の光が、小さく投影された太陽の像だと発見し、日食を観察したという話をつい思い出してしまう。宇宙と地球、自然と科学を結びつける一点の光を無数に纏った鹿を見る度に、僕は思わず動くピンホールだと心の中で呟くようになっていた。
西暦773年頃、兵庫県のある地域に全長6mに及ぶ巨大な鹿が住んでいたと伝承に残されている。鋭い角が七本に枝分かれし、目を鏡のように輝かせ、背中には篠が生え、脚には水かきが付いていたと言われている。巨大な鹿は、数千の鹿を従えて山を荒らし獣を殺していたが、やがて人里にまで危害を加えたことをきっかけに退治されるに至った。討ち取られる際に「このあと消ゆることなかれ」と言い岩盤に倒れた際の痕跡が今も残り続けている。他にも中国地方では人に危害を及ぼす鹿の話がいくつも存在しているのは、当時の人々にとって聖的な存在ではなく自然がもたらす力の象徴だったかもしれない。
中国地方の環境を振り返ると、近世以前からたたら製鉄が盛んな地域だった。炉に使う木炭が大量に必要だったため、中国地方のみならず近隣の山地で樹木の伐採が頻繁に行われていた。その結果、禿山や荒地になることは珍しくなかったと言われている。治山などの対策が行われるようになったのは江戸時代以降で、それ以前の山間部は土石流や水害など人々の暮らしや農業に甚大な被害を及ぼした。木の実や草など食料を失った野生動物はどこへ向かうのか考えると現代の鹿の行動と重なるところが見え、やるせなくなる。
ーー大学教員のAさんから聞いた話。
ゼミの引率とAさんの地元の案内を兼ねていくつかの資料館を訪れていた。その一つに土着信仰と神道が混ざった珍しい祭を紹介する文化会館を案内していたという。この地域では、ある動物を近隣の山々で狩り、供物として捧げる。その中にはある部分が裂けた個体が必ず一匹獲れると伝えられている。同行していた同僚のBさんがそのことを訝しく思ったのか、剥製を前に見ながら「そんなの迷信か何かだよ」と冷ややかに一蹴した。やや不信心な素振りに対してなのか、Aさんの地元もあって気を遣ったのか、学生たちは引きつった表情で苦笑いをするしかなかったようだ。各々がひとしきり館内の展示資料などを見終わり受付前に集まっていると、一人の学生が「Bさん、何か赤いものが付いてますよ」と言って肩あたりを指差した。Bさんは肩に手をやるとヌメリと重たい液体に触れたようで、指先に目をやると薄らと赤い液体が付いていた。どこかの天井から塗料が落ちるような場所はなく、怪我をする場所もない。学生が指摘するまで誰も気がつくことはなかった。その場にいた関係者たちは、いつの間にかBさんの耳からそれが何度も滴り落ちているのを見て、ある共通の想像をしてしまったが誰一人口にしなかったという。Aさんが恐怖心で押し黙る学生たちをかき分け、Bさんの耳を診ると小さく裂けてしまっていた。誰も耳を掻く姿を目撃していたこともなく、裂けた原因の検討もつかない。本人が痛みを感じてないのをいいことに、血混じりの吹き出物か何かだと誤魔化した。
深夜、僕は無事に目的とする高原まで運転することができた。ライトを持たず星々の明かりを頼りに丘を歩いていると、石笛のようなくぐもった高い音が辺りから聞こえはじめた。空気の震えは何かしらの予兆のようだけど、僕は気にせず先へ進む。傾斜を越えると山々が見渡せる場所に出た。星のように小さく見える街灯は、黄や橙などの色で発光していた。子供の頃、黒い画用紙に小さい穴を無数に開け、いい加減な星図を作って遊んでいたことを思い出す。日や街灯にかざすと小さな穴が光るのを見て静かに興奮したのを覚えている。彼方と此方を結ぶ穴が滲む様子は、未知のものが境界を越えてやってくるようだった。街灯から星空へと視線を移し、眺めていると、後を追ってきたのかいくつもの石笛が何度も強く吹いていた。一定の距離だったのが少しづつ近づいているようで、音の先に目を向けると、暗闇に沈んだ小さな鏡がゆらゆらと揺れている。それは二つ、四つ、六つ、八つとゆっくりと増え、数を数えるのを止めても増え続けていた。
守屋友樹 | もりやゆうき
写真家。2010年日本大学芸術学部写真学科卒業。写真の古典技法や古写真に関する歴史を学び、実地調査で過去と現在を重ね見る体験をする。かつてあった景色や物、出来事、時間などを想像する手立てとして不在や喪失をテーマに制作を行っている。 https://yk-mry.com/