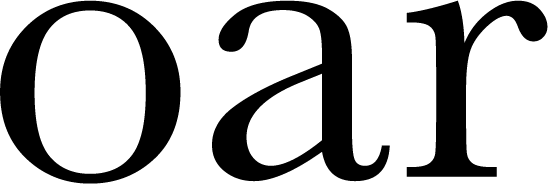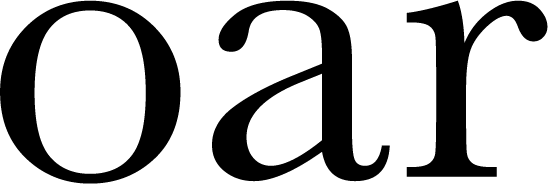未明の実験。未完の「トランスフォーム・モニュメント・リスト」

暗い部屋で、ひとつだけ灯した白熱電球に感熱紙をかざした。墨が垂れた様なシミが、触れた部分に瞬時に浮き上がっていった。光や熱や音や電気や運動、いつだって放出されるばかりだった「熱量」のそのひとつを閉じ込めた瞬間だった。この惑星では、小さな熱量から順番に安定した状態へ向かってしまうから、できるだけ効率よく電気や運動に変換することがよく行われる。だから白熱電球の僅かな放出の熱量は、本来なら変換も間に合わず失われてしまう筈だったが、その姿は感熱紙に残すことができたのだった。
フランシス・ポンジュは『蠟燭』の詩の中で、ロウソクの火を金色の葉に例えた上でこのように記している。
「みずぼらしい蛾たちは、森を霞ませる、あまりにも高く懸かった月よりは、好んでこの植物に襲いかかる。だがたちまち火に焼かれ、角突き合いに疲れ果てて、みな、昏睡状態に近い熱狂の縁に身を慄わせる。」
燭台の上のロウソクの火は照明として使われていたが、ポンジュは、火に飛び込んでしまう蛾が、火自体の持つ熱によって直接的な影響を与えられていることを、単にダメージに変換しない視点で状況を観察している。「熱狂の縁」という燭台の縁に降り立った蛾が、身を慄わせる理由は火による痛みなのか、恐怖か。またはトランス状態への陶酔だろうか。
白熱電球やロウソクの光熱は、別の媒体を介すことで一時的な熱量を別の形で残すことになった。その成果物は、発端の熱量が失われた際、元の要素を殆ど有さない記念碑として生まれ変わるのだ。
熱量の碑をつくろうか。
ある土地の偉人、ゆかりの出来事、名詩。人は昔から碑(ひ)をつくることで大切なそれらを後世に残そうとしてきた。でないといつかきっと忘れてしまわれる。それと比べようも無いほどに、白熱電球の光熱のような微小の熱量の数々は、忘れられる以前、気付かれることもなく放出と同時に傍から当たり前に失われてしまっている。
ここに熱量の碑をつくろうか。どこまでも小さくて、どうしようもなく些細なものだ。熱量が残していく感熱紙の表面に浮かぶシミのような姿。碑(ひ)は碑(いしぶみ)とも言うのだからやはり石で作るべきでしょうか?そんな事はない。すぐに姿をくらます熱量に対して最適な素材選びは、その場で調達することで新鮮ささえ手に入れられるだろう。
白熱電球の光を頼りに書き留める。
ーー砂漠の碑
砂の波模様
ーー日照りの碑
ベランダで乾き切った洗濯物
ーー路上の碑。
紙くず、プラスチック容器、何かの破片。ゴミ
ーー空気の碑
遠くの山から上がる狼煙
ーー空の碑
飛行機雲
ーー冬の碑
白い息
ーー雨の碑
増水した川
ーー太陽の碑
成長し続ける草むら
ーー屋上の碑
排水されない雨水
ーー火の碑
灰
ーー迷子の碑
北を探すコンパスの針
ーー傷口の碑
かさぶた
ーー彫刻の碑
型
ーー髪の毛の碑
抜け落ちた先尖毛
ーー
ーー
ーー
机上の旅から帰ってきて、碑は群を成し極相に達した。外は明るくなり始めていた。
僕は部屋から出ると、車に乗って少し走ることにした。
道すがら、次々と迫っては通り過ぎていく新生の碑を追うのに必死になった。まるで違う景色を見ているようだ。
でもこの惑星もいずれは部屋の片隅になり得るかもしれない。
あるいは他の媒体に熱量が置き換わり、全て放出し切ってしまうのだろうか。膨大な熱量だ。
ーーー熱量の碑
離陸の準備を整える宇宙ロケット
離陸上昇に特別な場所は必要としない。晴れた静かな空があればそれで大丈夫だ。

2022年12月
引用:『フランシス・ポンジュ詩集』阿部良雄編訳 小沢書店 1996年より
大石 一貴 | おおいし かずき
1993年山口県生まれ。彫刻家。Studio&Space「WALLA」を共同運営(https://walla.jp)。2018年武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻コース修了。東京・有楽町のソノ アイダ♯新有楽町で行われている「ARTIST STUDIO 第8期」に2023年1月15日(日)まで参加中。国際水切り大会8位。https://www.kazukioishi.com