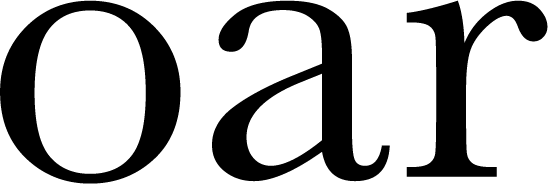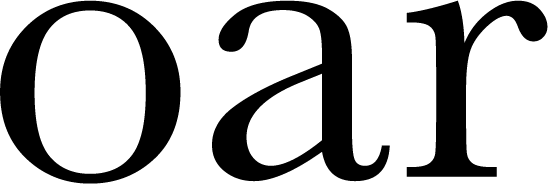第三回
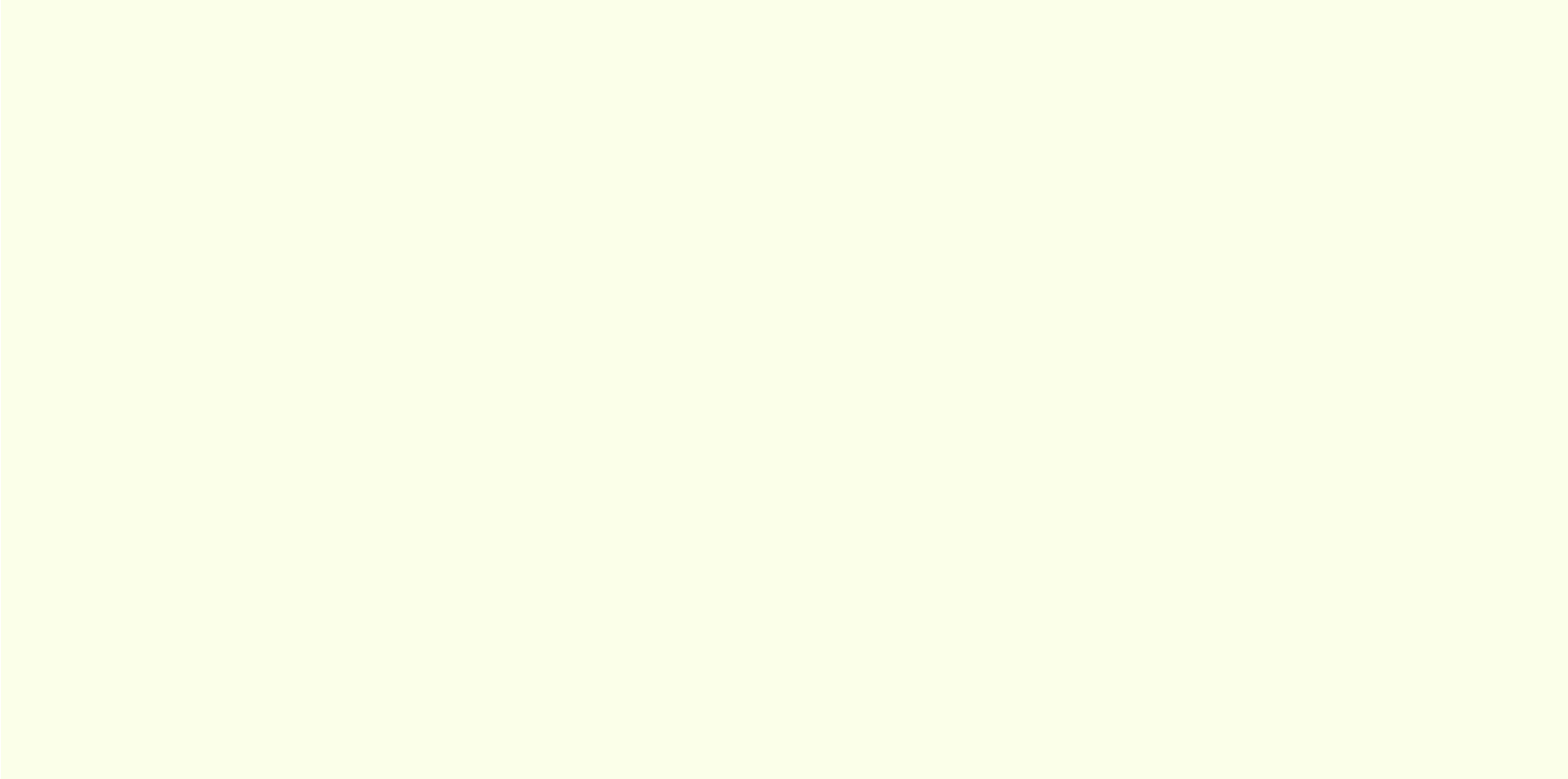
この瓶には、この前まで梅干しが入っていたよ。今はりんごのジャムで、その前はトマトソース。はちみつ。さらにその前は、もう覚えていない。
火がまるごと届いた贈り物。燃えていて、どうやってここまで来たのだろう。
中に入っていたものはみんな、はっこうしていた。においも強く、凝縮していた。
りんごのジャムは光の道の味がした。
この世界に、人は、たくさんいる。かおも、人生も、声も、なにもかもちがう人たちが。ちがう料理を食べ、今寝ていたり起きていたりする。そのことに、瓶はいつも、驚く。
貼られたラベルの跡は、すぐに擦れて消えていく。
大丈夫だよと、声をかけられる。優しい声。
冬晴れ。 遠くには雲が薄く伸ばされている。
今日はどこかに行ってみようかしら。そう思ったが、身体はひとつしかなく、この身体は、どうも鈍くて重い。手足は冷たく、固くなっている。あなたと過ごした時間が重しになっているのだろうか。
それでも冬の太陽の光はまっすぐ届く。
それに見合うように体をピンとしてみる。すると重しは、ぐっと下がり、わたしの足腰を、すこし丈夫にするようだ。風はつめたく、頬が乾いてゆく。
夜勤明けで家に帰る道の。
この、大きな公園。朝が始まって、歩いている人たちのなかに紛れて、落ち葉が落ちてくる。大人が佇んでいるわきで、子供が不思議な遊びを見つけているのを、遠くから見る。
でも、ここは、開発でなくなってしまうかもしれないのだという。そうしたらこの景色は、どこへいってしまうのだろう。
ここを通るたびに、消えていく生き物たちと子供たちの百鬼夜行が、薄い紙の立体になって静かにすすんでいくのが見える。
大きな影に織り込まれた悲しさの色。
このままこの公園を失ったら、わたしの夜勤明けは、ほとほとバッドエンドになってしまうのかもしれない。
少し休んで、また、世界に出会えるためには、未整理の世界が必要なのに。
絶望する。
でも、わたしはあなたに会って、あなたの重しをうけとる。 あなたがいつも、くれるから。
わたしがいる、ここは、ほんとうは、ふしぎな光り方をすること。
世界の落とす影の柔い色合い。
水晶玉が隠れているかもしれないこと。
それは、柔らかい道を歩けばきっと、見えてくる。たくさんのものを拾って、直してきた人の背中も。
光が、ふいにやってくる。疲れたときや、もうやめたいとおもったときに。それを手に、お面に、擦り込む。
複雑なにおいや味が、一層たちこめてゆく。その瞬間に立ち会う。
そのことには喜びがある。
家の周りは、ひっそり閑。
正月飾りをつくればよかった。でもみんなが仕舞ったときに、作って飾ってしまおう。
すこし眠ったあとに、外に出た勢いでバスに飛び乗った。
森の奥の、休憩所には、ばらばらといろんな年代の人がいて、なにかの解説を見たり、木を触ったりしていた。
草や露は、かすかに目を合わせる。
わたしは座って、持ってきたお茶を飲みながら、わずかな陽を体に蓄えるようにして、ベンチで童話を読んだ。
栄えた町の駅では、ぬいぐるみを売っている人がいた。前に欲しかったキャラクターのストラップもあったが、迷って買うことができなかった。
そこからすこし外れたところでは、お茶碗を一つ置いて、自分の境遇についてノートに書いて立てかけている人もいた。
わたしは通り過ぎる。
通り過ぎるひとびとという集団になってしまう。
お墓の奥には、お粥やお味噌が眠っている。
人は、みんなのこらず、生きているから。
もっとなにかをたすけられたらいいのにと、いつもおもう。
多くのものに頼って生きているわたしの体と心は、もっともっと、他人に分けられる、そんな気持ち。
でも そうね。
その後に、消え入り、ひとりぼっちの幼い子供になることで、わたしは二枚の貝になる。
貝殻はお面になっている。そのなかに、透明な球が入っていて、わたしが関わる人の顔がうつっては消える。
牛がぶすっと鳴くのが聞こえる。
プラスチックに絡まった鳥も鳴いている。
ぼろぼろのお茶碗は、世界の誕生日の夢を見た。たくさんの人が、蝋燭を何本も何本もたてて、もういなくなったすべてのものと、これから生まれるすべてのものに、スペースを用意して、祈っていた。
その背の低い蝋燭は、お仏壇用のものだったけれど、だれも気にせず、きれいだね、きれいだね、と口々に言っていた。お茶碗には玄米がよそられた。
わたしもそれを、いただいた。
あたたかい昼間が去り、寒い夜が覆い被さる。
コートのほつれたところを縫ってしまわないと、そこからでていってしまう。
わたしのおへそのあたりからあたらしくなってゆくみたい。
なっていけたらよいのに。
ほんとうは、沈黙のことをみんなに話したいのに。
たっぷりと、ゆっくりと、空から降ってきたみたいに。
そうしたら、器にはなにが盛られるのと、花はおへそに聞いた。
なんにもないよ、と、おへそがこたえた。
高田満帆 | たかだまほ
東京都拠点。絵や立体、文章、4コマ漫画、パフォーマンスなどを制作するほか、介護の現場にも携わっている。Instagram:@mahohoyu