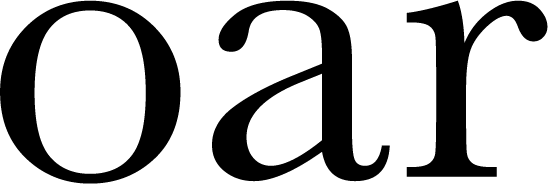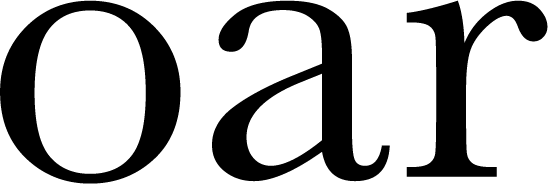第二回

花壇に白髪がおちている。豆乳をいれた紅茶に泡がたくさん。黄色いコップに小蝿がとまり、束の間、時間が夜へゆく。
冷蔵庫をあけて、スーパーで買った野菜たちを見る。キャベツ、ゴーヤ、つるむらさき。夏野菜の終わり。キャベツやゴーヤの断面が細胞に見え、つるむらさきのひややかな茎や葉を想像しては、口の中が粘る。じぶんの手をなんどもひるがえしてみた。油揚げの茶色、お豆腐の白。母親の手。
理科の資料集をなくして、2冊目を買ってもらわなければいけなかったとき、母に言うのにひどく時間がかかったことを思い出す。
あのスーパーには店員が誰もいない。客は金額をオブジェのなかにいれていく。そのたびに、針金のさきについた野うさぎや茶色の蝶の紙細工は揺れ、丸みを帯びた白い陶器の胴からとても綺麗なおとがする。
隣には、ちいさなミュージアムがついていて、なにも展示されてはいないけれど、なにかを見ようときた人たちがかならずいる。その人たちを見ていると、わたしもまた、見られている。
あたたかいお茶をいれると、鳩時計がでてきて、ひとつないた。
葉に湛えられた水がしたたりながら、よく澄んでゆく。台所の窓から、ヤモリの足が透けて見える。捕まえてみたいという気持ちと、捕まえる自分が恐ろしく感じられる気持ちと合わさって、窓をつつく。動かなかった。窓を開けたら、きっと挟まってしまう。
開封されない思いは、夜を越え、発酵する。それらが閉じ込められた手紙の封を、わたしはあけられない。でもそれは鏡になってゆく。思いをすべて跳ね返す鏡に。しずかに目をつむって、はりついたあきらめが少しずつ剥がれて、皮膚がぼろぼろになっても変身して、空気にふれようと、おもって、そして、跳ね返る思いを、しばし眺めて。
映画のなかで大切なことをいう老婦人の、靴下や、まくらの美しいはだにあらわれやすいものたちがならぶ。彼女たちに会えるのはいつだって夜だったから。
むこうの空を鳩時計の鳩が飛んでいく。いつぞや、夢のなかでたすけてくれたカラスも飛んでいく。濃紺の空には水色、ほんの少し白ちゃけた黄色がまざっている。
層になった雲のように、響きがやってきては、この時間はあまりに美しく、なににもかえられないとかんじる。不協和をつくりながら、それをしずかにきりひらくあのうたはどこだろう。輝きとふあんていなよろこびの声。ちょっとした洗い物をし、なにかを流しながら。きっと。
過ぎたばかりの季節を思い返しては、もうこんなに肌寒くなったことに体はしっかりと反応しており、鍋の夢。磨かれた鍋の底にわたしがうつって離れなかった。
描きかけの絵にさいごに筆をのせた日に照りつけていた陽はざっと過ぎてゆき、未完のものたちが、寒々とした空気に包まれている。
かぼちゃが店先にならぶ。
雨の日には、けげんな人の顔がならぶ。
わたしたちの少しばかりの余裕は、ほとんどたべものとおなじで、すくなくともわたしにとってはおなじで、スーパーにならぶ。傘の柄や、ぬれそぼる植物たち。なぜかびしょぬれのひともまた。
道に咲いている野の花の、その隣の野の花もまた、おなじように風にふかれながら根をはっている。
この夜が、たったこれだけのために、世界に別個に存在した灯りだとして、蛍光灯の光はそっと消される。物語の中の、職業が名前になった人たちが夕食を食べる。わたしは食べず、それを見つめ、彼らの食事が終わったらあなたと食べたい。
ともにいることを受け入れながら、時に、跳ね返される力にお面を歪められても、その反発はまた、わたしのものでもあったから。
拳ほどの鏡ばりのお面を、洗ったばかりのお皿に浮かべて玄関に飾った。
お面は夜の何も映さず、ただそこで沈むように傾いている。
白い巾着に、明日のためのりんごを入れる。
いつのひにかひろった鳩の羽をみる。だれかにもらったものかもしれない。
底は遠く、計り知れないが、手を入れると、とろりとした水が皮膚にまとわりつく。米を研いだときみたい。外は静まり、寒さを抱えた人たちが家路に急いでいる。
とおくにくちぶえを重ねて、みなの健康をいのりながら。それが果たされることは、いつもありえなく、でもそれを、願いながら。
やってくる朝を受け入れる。
汚れた下着が空に舞う朝を。
高田満帆 | たかだまほ
東京都拠点。絵や立体、文章、4コマ漫画、パフォーマンスなどを制作するほか、介護の現場にも携わっている。Instagram:@mahohoyu